食べ物でだるさを解消する対処方法や対策・原因・特徴について

だるさとは
最近、身体が何となくだるいと感じている方は多いことでしょう。身体がだるいのを改善してくれる栄養剤なども多く販売されていますし、テレビをつければそういった栄養剤のCMがよく流れます。このことからしても、現代にはこうした「だるさ」に悩み、その改善策を求めている人がどれほど多いかがうかがえますね。
そもそも、だるさというのは肉体的にも精神的にも、自分の限界を超えた仕事や出来事に直面した時、その回復のための休息を必要としている状態のことを言います。「疲労感」と呼ばれることもあります。
一時的に身体や心のパフォーマンス(機能)が落ちてきたら、それは疲れていると言えるでしょう。
だるさというものは、熱や痛みと同じで、我々人間がこれ以上体調を悪化させないために、健康な身体や心を保つために出された「危険信号」何だと考えて下さい。
朝起きるのがつらい、気力がない、やる気がない、何をやるにしても集中できない、考えがまとまらない、食欲がない、肌が荒れる、目が疲れる、肩がこる、頭痛に悩まされている…そのような経験をしたことはありませんか。
もしそのような経験がすこしでもあるとすれば、それはだるいという証拠です。放っておくと、心身の様々な不調につながる恐れがあります。
文部科学省が2004年に一般地域住民2742名を対象にして行った疫学調査によれば、現代の日本人のおよそ6割がだるさを感じているという調査結果が出ています。
だるさの特徴(症状)や原因
その大きな特徴は、心身ともに疲れている状態であっても感じにくいということです。例えば、達成感のある仕事ややりがいのある仕事をしていたり、夢中になってスポーツに打ち込んでいる時などには特に感じにくくなります。
そのまま放っておくと、気が付かないうちに自分の限界を既に超えていて、精神的に病んでしまうことも稀ではありません。
また、どんなに休養をとっていても、だるさがなかなか改善されない場合、重大な病気が潜んでいる可能性がありますので、注意が必要です。
だるさの原因はやはり、忙しい毎日が引き起こす過労の蓄積や休息不足、栄養不足に他なりません。
毎日無理に働きすぎて疲れがたまっていたり、生活が不規則になっていたり、睡眠が充分にとれなくなったりしていませんか。こういった状態だと、だるさが生じやすいのは明白です。
栄養バランスの偏った食事もだるさのもと。現代はファーストフードやインスタント食品などの普及で、バランスのとれた食事がしにくい時代になりました。
特に現代人にとって不足しがちなのがビタミンやミネラルです。身体の調子を整え、さらには精神状態を安定させ、うつなどの「心の病」を改善・予防するのにも大切な栄養素です。しっかり摂るようにして下さい。
その他の原因としては、風邪やインフルエンザなどに代表される感染症による体力の消耗、貧血や心肺の疾患による酸素の欠乏、筋肉や神経の不調、化学物質などによる環境の影響などが考えられます。
だるさの対策
では、だるさの解消法には、具体的にどのようなものがあるのか。
だるさの原因がわかっていて、特に目立った症状がなければ、休養をしっかりとり、栄養補給をするようにしましょう。市販の栄養ドリンク剤も利用するのもおすすめです。
特に代謝を高め、疲労回復を促し、だるさを改善するビタミンB1を積極的に摂取するようにしましょう(このビタミンB1の効果的な摂取方法については後ほど詳しく説明します)。
だるさがなかなかとれず、長く続いたり、発熱・顔色が悪い・尿や便の異常・体重減少・咳・息切れ・むくみなどの症状を感じる場合、医師の診察を受けるようにして下さい。
休養してもだるさがなかなかとれない場合、貧血・更年期障害・シックハウス症候群・慢性疲労症候群(CFS)である可能性があります。
また、日頃から疲れにくい身体をつくることを心がける必要があります。そのためには、身体の疲れをためない習慣を送るようにしましょう。
例えば、休息や睡眠は仕事がない週末にまとめてとるのではなく、日頃からこまめにとるようにすれば疲れがたまりにくくなります。
入浴も大切。ぬるめのお湯につかれば自律神経が落ち着いた状態になり、心身ともにリラックスします。
体力を付けることもだるさ予防には役立ちます。ウォーキングなど、無理のない軽めの運動をとり入れてみましょう。運動後は、クールダウンもしっかりとり入れましょう。運動を急に中止にするのではなく、深呼吸やストレッチも行うようにして下さい。
食べ物でだるさの解消方法
だるさを解消するには、良質なたんぱく質、そしてビタミンB1を摂取してスタミナを付けるのが最も良い方法です。ビタミンB1は血液中の糖分をエネルギーに変えるためには欠かせない栄養素です。もし不足してしまうと、エネルギー消費が上手くいかず、スタミナ不足になり、疲労が蓄積して身体がだるくなりやすくなります。
豚肉は良質なたんぱく質やビタミンB1が豊富に含んでおり、スタミナをつけるのに非常に適した食べ物です。できれば、脂肪分が少ないヒレやモモなどの赤身の肉を食べたほうが良いでしょう。
ただし、ビタミンB1は単独で摂取すればそれで良いというわけではありません。実はビタミンB1は非常に摂取しにくい成分でもあります。
水や熱に弱く、たとえ必要量以上摂取しても体外に排出されてしまいます。そのため、非常に吸収されにくい栄養素なのです。
そこで、豚肉をにんにくと一緒に食べることをおすすめします。
疲労回復には効果的だとして有名なにんにくには、アリシンが含まれています。殺菌作用があり、胃液の分泌を促し、消化や食欲を増進させる働きがある成分です。このアリシンが、ビタミンB1を効率良く摂取するのを助けてくれるのです。
アリシンはビタミンB1と結合すると、アリチアミンという成分に変化します。
アリチアミンは熱や水にも強く、必要量以上摂取しても体外に排出されることもないので、効率良くビタミンB1を摂取できるようになるのです。
豚肉を食べる際は是非、にんにくと一緒に食べてみて下さい。
食べ物でだるさの解消のまとめ(未然に防ぐ方法など)
だるさは、心や身体が疲れた状態であることをしらせる「危険信号」です。しかしこの危険信号になかなか気付かず、放置してしまう人は多いです。しかしそのまま放っておくのは良くありません。
日頃から、疲れにく身体をつくる習慣を送る必要があります。適度な休息や睡眠をとったり、ゆっくりとお風呂につかったり、無理のない軽めの運動をする習慣がつくと、身体に疲れがたまりにくくなり、だるさ予防につながります。
栄養補給も大切です。特に現代人はビタミンやミネラルが不足しがち。こうした栄養をしっかり補うようにしましょう。
だるさを解消するうえで特に重要な栄養素はビタミンB1です。ビタミンB1は血液中の糖分をエネルギーに変える栄養素です。もし不足してしまうと、エネルギー消費が上手くいかず、スタミナ不足になり、疲労が蓄積して身体がだるくなりやすくなります。
ビタミンB1を効率良く摂取するにはにんにくと豚肉を一緒に食べるのがベスト。
豚肉に含まれるビタミンB1は非常に摂取しにくい成分でもあります。水や熱に弱く、たとえ必要量以上摂取しても体外に排出されてしまいます。そのため、非常に吸収されにくい栄養素なのです。
にんにくに含まれえいるアリシンは、殺菌作用があり、胃液の分泌を促し、消化や食欲を増進させます。このアリシンが、ビタミンB1を効率良く摂取するのを助けてくれます。
ちなみに、だるさに悩んでいる方の中にはどんなに休養をとってもだるさがとれない方もいるでしょう。このような場合、何か深刻な病気を患っている可能性がありますので、必ず医師に相談して下さい。
-

-
解消法 授乳中の頭痛を解消する対処方法や対策・原因・特徴につ...
出産は女性にとってとても負担がかかる大変な事です。その為、出産後の女性の体は大変疲れた状態になっています。授乳をするだけ...
-

-
解消法 ツボで手のむくみを解消する対処方法や対策・原因・特徴...
体の中にはむくみやすい場所があるとされています。よくむくむのは朝に顔がむくむ状態です。夜は寝ていますが横になることが多く...
-

-
解消法 しわ・たるみを解消する対処方法や対策・原因・特徴につ...
年齢と共に増加してしまう”しわ・たるみ”。顔だけではなく、手やひざや首など体全体に出てしまい、ぱっと見た感じ相手に対して...
-

-
解消法 虫歯の頭痛を解消する対処方法や対策・原因・特徴につい...
子供と言いますと虫歯の子が多いです。甘いものをたくさん食べて、歯磨きをしないからのように考えるかもしれません。実は別のと...
-

-
解消法 気圧による頭痛を解消する対処方法や対策・原因・特徴に...
骨折などをした人に関してはある不思議な現象があります。その人に聞くと天気がわかります。特にこれから雨が降る、嵐が来るなど...
-

-
解消法 ビールでイライラを解消する対処方法
人は社会で生活する時、いろいろな人とと関わりながら、いろいろなルールの元で行います。すべてが自分の考えている通りに動けば...
-

-
解消法 グッズで運動不足を解消する対処方法や対策・原因・特徴...
起きていると寝ている時があります。寝ているときはベッドなどに横たわっていて記憶は何もない状態です。多くの場合はベッドに横...
-

-
抱き癖を解消する対処方法や対策・原因・特徴について
抱き癖とは、赤ちゃんの頃に抱っこすれば泣き止む・大人しくなるというようなひとつの赤ちゃんの性質のようなもので、特に過去か...
-

-
解消法 幼児の便秘を解消する対処方法や対策・原因・特徴につい...
小さなお子様でも便秘をする事があります。幼児はまだ排便能力が大人のようにまだ発達していません。その為、乳幼児期は便秘にな...
-

-
解消法 寝起きの頭痛を解消する対処方法や対策・原因・特徴につ...
頭痛とは色々なパターンと種類があります。その種類大きく分けて「慢性」「症候性」「日常性」がありますが、慢性の中にはさらに...
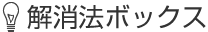

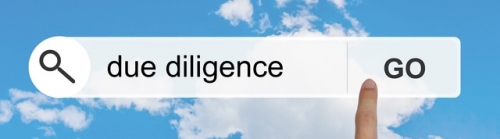
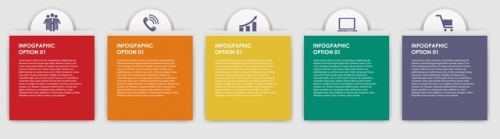




最近、身体が何となくだるいと感じている方は多いことでしょう。身体がだるいのを改善してくれる栄養剤なども多く販売されていますし、テレビをつければそういった栄養剤のCMがよく流れます。このことからしても、現代にはこうした「だるさ」に悩み、その改善策を求めている人が…