解消法 胃の膨満感を解消する対処方法や対策・原因・特徴について

胃の膨満感とは
口から入った食事に関しては咀嚼をされた後は食道を通り、その後胃に送られます。胃においては胃酸があり非常に強い力で食べ物を消化します。その後の部分である腸などに送られて吸収されるようになります。一応胃酸がたくさん出て消化を進めてくれますが、かと言って次から次へを消化をするわけではありません。人にはそれぞれ処理能力がありその力も異なるとされています。
あまり食べられない人もいれば大食いファイターのようにどんどん食べることが出来る人もいます。大食いファイターだから胃酸が多く出たり消化が早いわけではないようですが、普通の人よりも機能としては優れているとされています。沢山食べるとどんどん胃にためられていってそのうちいっぱいになるとお腹が一杯の状態になります。
満腹の状態です。胃はプラスチックや鉄のように硬い臓器ではないですから、常に一定量しか入らないわけではありません。ゴム風船のように適度に伸びるようです。ですからお腹いっぱいになったとしても好きなものであれば隙間を作って食べることが出来る場合があります。
そうは言いながら限界があり、もうこれ以上はいらないとなった時に胃の膨満感を感じるようになります。通常の場合はそのままの状態にしていれば少しずつ食べ物が消化されていき、どんどん胃からはなくなって行きます。ですから気にする必要はありません。しかし場合によってはこの状態が続くことがあります。少し苦しさもあります。
胃の膨満感の特徴(症状)や原因
食事をした時にお腹いっぱいまで食べるとどのようになるかです。食べ放題のお店などに行くと元を取ろうとどんどん食べます。焼肉店であれば3千円で食べ放題のお店があります。多くの人は元が取れないようですが、取ろうとすればかなりいっぱいになり、更にその上から詰め込もうとすることがあります。
帰りなどは苦しくて歩けないこともあります。胃の膨満感の特徴としては、たくさん食べ過ぎてもう食べられない状態に近い状態です。これは食事において起こることが多いですが、水分でも起こることがあります。水をたくさん飲んだ時に、もうこれ以上飲むことができないくらい飲むことがあります。その時にも膨満感を感じることがあります。
見た目としてお腹がぼっこりと出て明らかに食べたものが見えることもありますし、痩せている人であればあまり食べていなくても膨満感を感じることがあります。原因としては口からたくさんのものが入ることにより、それが胃にたまることによって起こります。まず食べ物があり、その他には飲み物があります。
その他に意外なものとしては空気があります。食事をしたり日常生活をするときにどんどん空気を口に入れます。それが胃にたまることによって膨満感を感じることがあります。この空気に関してはそのまま腸などを通って最終的には体外へ排出されるようになります。空気などは口から出て行くように感じましたが、胃の中に入ればそのまま膨らむ要因になります。
胃の膨満感の対策
胃の膨満感に対する対策としては食べ過ぎと飲み過ぎを防ぐことです。食事をするときに満腹になるまで食べる人がいます。子供の時であったり、スポーツ系のクラブ活動をしている時であればまだいいでしょう。食べた分消化をします。でも大人で一般的な生活をしている人であればそれほど活動をするわけではないのであまり食べ過ぎれば余った分が脂肪としてついていきます。
体にもよくありません。飲み過ぎに関しても同様です。食べ物は食べずにどんどん飲む人がいます。お酒を飲むのも問題ですが、それ以外にジュースなどを飲み過ぎるのも良くないとされています。腹八分目と言われることがあります。満腹状態に比べて8分目くらいで食事を辞めることです。
食事が出された時、少し残すぐらい、もう少し食べられるぐらいのところで辞めるようにすると良いとされます。そうするにはあまり大皿などに出さないことが大事です。家族が多いと一人一人に出されるのではなくて大皿で好きなだけ食べられることがあります。居酒屋などでも個人で注文せずにどんどん注文をして参加者で食べることがあります。
残っているともったいないとおなかがいっぱいになっているのに食べてしまうために膨張してしまいます。食事をするときには自分だけの分量がわかるように工夫をし、外食などでも食べる量をコントロールするようにします。そうすれば満腹まで食べるようなことが少なくなります。自宅でも量を減らしてもらいます。
胃の膨満感の解消方法
胃の膨満感の解消方法としては胃腸薬があります。一般の薬以外に漢方による胃腸薬も知られています。漢方薬は薬ですが自然の生薬などが使われているので効果がゆるやかになります。もちろん薬に頼らないのがいいですが、飲み会などではつい食べ過ぎ、飲み過ぎてその後に膨満感を感じることがあります。食べた後に飲んで効くタイプのものを飲むようにします。
先に飲むタイプの場合は沢山食べることがわかっている場合です。食事において膨満感を得ることが多い人は水分を取るようにします。水分と言ってもお酒ではなくお水であったりお茶などです。これらによって先に膨満感を得ていれば食事を取ることができなくなります。
水などであればカロリー自体はありませんから、その後に脂肪などとして残ることが少なくなります。太り過ぎなどが気になっている場合は、水分を利用して膨満感を得るようにして食べ物を食べないようにします。また食べるときにおいても食べる食材に気をつけます。肉類、炭水化物は結構どんどん入ってしまいます。
ご飯であったり締めのラーメン、うどんなどは食べることができます。それ以外に野菜であったり海藻に関するものなどを食べるようにします。これらについても野菜などで膨満感を得られるようにしていれば後で肉などを食べにくくなります。うどんなどが目の前にあっても食べることができません。そのような効果を期待することができます。寒天なども事前に食べるのに効果的です。
胃の膨満感のまとめ(未然に防ぐ方法など)
胃の膨満感における未然の予防方法としてはストレスを溜めないことがあります。多くの人は食事や飲むときにストレス解消で行うことがあります。男性であればお酒を飲んで食べてになるでしょう。女性の場合は食べてが多いかもしれません。スイーツのバイキングや食べ放題などを利用することがあります。ストレスがなければそのようなことを感じることは少ないでしょう。
これだけ食べたら体に異常をきたすなどがある程度は予測することができるからです。ストレスがなければ食べたり飲んだりしてストレスを解消しようとすることがなくなって胃の膨満感も得にくくなります。正しい食生活について勉強することも膨満感を予防する方法の一つになります。
食育と呼ばれる言葉があります。主に子供に対して正しい食事などを教えることを指しますが、子供に教える立場である親が食のことについてきちんと理解していない場合があります。栄養分にはどのようなものがあり、それらがどのような作用があるかなどです。そのようなことを自分で学ぶようにすれば、無理な食べ方などをしなくなるでしょう。
学ぶことによって自分の体だけでなくて家族の体を守ることもできるようになりますから一石で何鳥にもなります。食育の方法としては家族で行うのもよいでしょう。自分だけで学ぶのではなく、普段食事をする人、食べる人が一緒になって勉強していけば食べる量のコントロールなどをすることができるかも知れません。
-

-
解消法 高齢者の便秘の解消する対処方法や対策・原因・特徴につ...
便秘になるとお腹が苦しくなってしまいとても辛いですよね。そんな便秘に、特に高齢者の方はなりやすくなってしまいます。加齢と...
-

-
解消法 老け顔を解消する対処方法や対策・原因・特徴について
老け顔とは、自分の本来の年齢よりも顔が年上に見えることです。たとえばまだ20代なのに30代や40代に見られたり、まだ40...
-

-
解消法 新生児の便秘を解消する対処方法や対策・原因・特徴につ...
新生児の便秘と聞いて、驚く人もいるのでは無いでしょうか。実際に小さい赤ちゃんでも、なかなかうんちが出なくて、困るときもあ...
-

-
解消法 黒ずみを解消する対処方法や対策・原因・特徴について
昔の子供といえば外を駆けずり回って遊んでいたといわれています。今の子供はどうかですが、いろいろな事情があってなかなか遊べ...
-

-
解消法 頭痛をストレッチで解消する対処方法や対策・原因・特徴...
あまりに日常的にある痛みの場合は病気との認識を持たないことがあります。また一定期間経つと痛みが軽減したりするときも重大な...
-

-
解消法 歩く事で便秘を解消する対処方法や対策・原因・特徴につ...
基本的に便通というものは、毎日定期的にあるというのが健康な状態といえます。理想を言えば、毎朝の大体決まった時間にあるとい...
-

-
解消法 妊娠のつわりを解消する対処方法や対策・原因・特徴につ...
妊娠すると女性の体には様々な症状が現れてきます。その中に”つわり”があります。この妊娠のつわりとはどの様なものなのでしょ...
-

-
解消法 テニスボールで肩こりを簡単に解消する対処方法や対策・...
日常生活を送っていると様々なストレスにさらされます。本人は意識をしていないが、いつの間にか緊張状態にあったり、多くのプレ...
-

-
解消法 足の冷え症を解消する対処方法や対策・原因・特徴につい...
女性は冷え症になってしまう人が多くいます。その中でも足が冷えてしまう人はとても多いのではないでしょうか。冬でもないのに足...
-

-
解消法 お腹が張るを解消する対処方法や対策・原因・特徴につい...
社会生活をしていると色々な体調不良が起こってきますが、特に胃腸関係の不調や不具合は慢性化しやすく、気分的にも厄介な症状に...
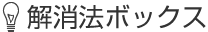

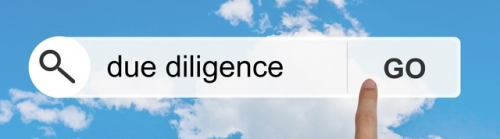
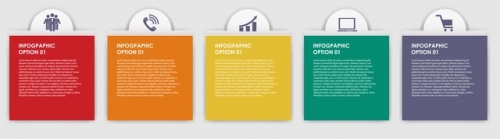




口から入った食事に関しては咀嚼をされた後は食道を通り、その後胃に送られます。胃においては胃酸があり非常に強い力で食べ物を消化します。その後の部分である腸などに送られて吸収されるようになります。一応胃酸がたくさん出て消化を進めてくれますが、かと言って次から次へ…